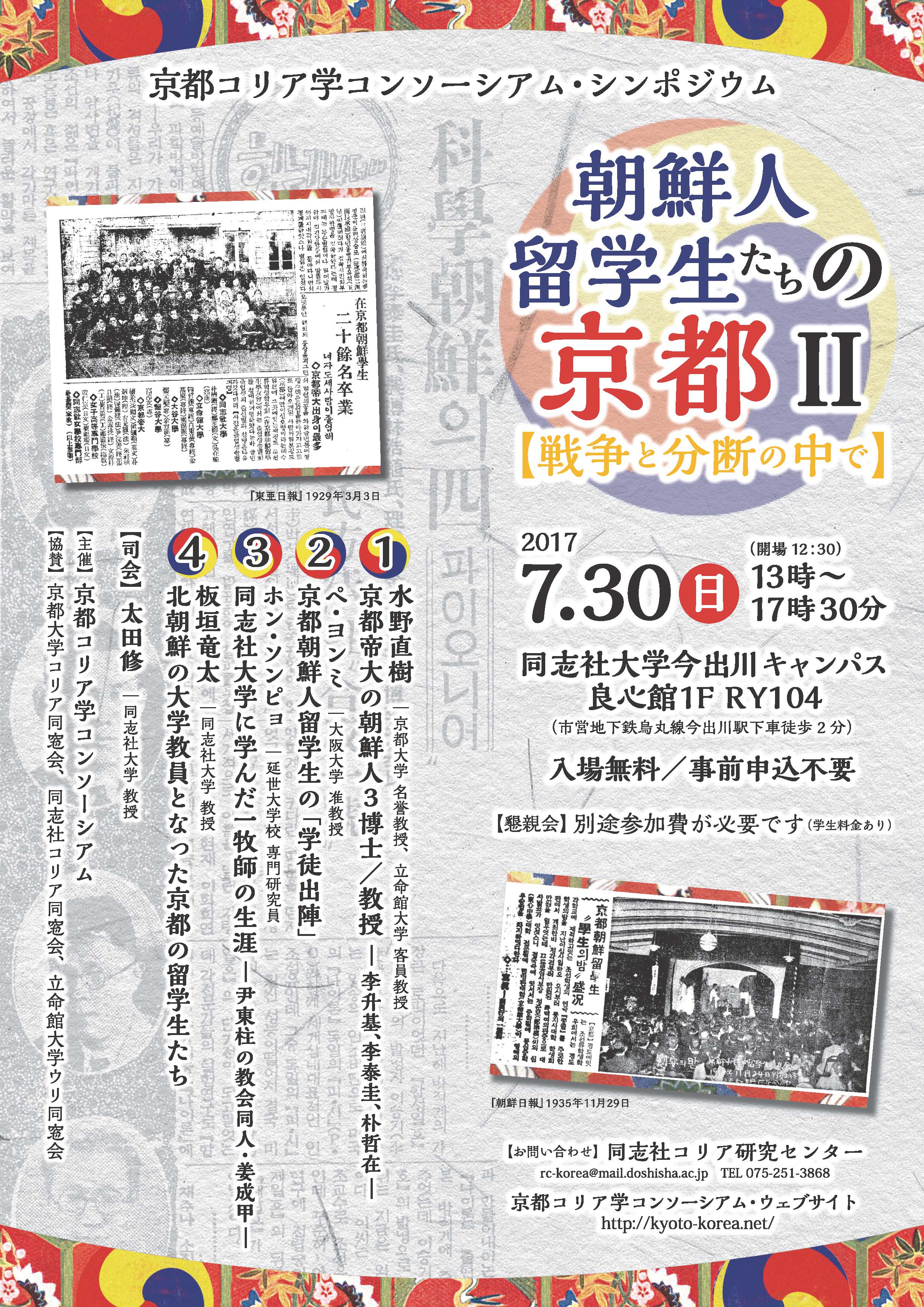
日時: 2017年7月30日(日) 13:00~17:30 (開場12:30) ※入場無料/事前申込不要
場所: 同志社大学今出川キャンパス 良心館1F RY104(キャンパスマップはこちら)
※京都市営地下鉄烏丸線・今出川駅下車・1・3番出口から徒歩2分(交通アクセスはこちら)
司会:
太田修(同志社大学 教授)
発表:
1.水野直樹(京都大学 名誉教授・立命館大学 客員教授)
「京都帝大の朝鮮人3博士/教授 ―李升基、李泰圭、朴哲在―」
2.ペ・ヨンミ(大阪大学 准教授)
「京都朝鮮人留学生の「学徒出陣」」
3.ホン・ソンピョ(延世大学校 専門研究員)
「同志社大学に学んだ一牧師の生涯 ―尹東柱の教会同人・姜成甲―」
4.板垣竜太(同志社大学 教授)
「北朝鮮の大学教員となった京都の留学生たち」
※発表は主に日本語でおこなわれます。
主催: 京都コリア学コンソーシアム
協賛: 京都大学コリア同窓会、同志社コリア同窓会、立命館大学ウリ同窓会
※懇親会: 別途参加費が必要。学生料金あり。
【お問い合わせ】
・同志社コリア研究センター E-mail: ![]() Tel: 075-251-3868
Tel: 075-251-3868
・京都コリア学コンソーシアム(KCKS) HP: https://kyoto-korea.net/
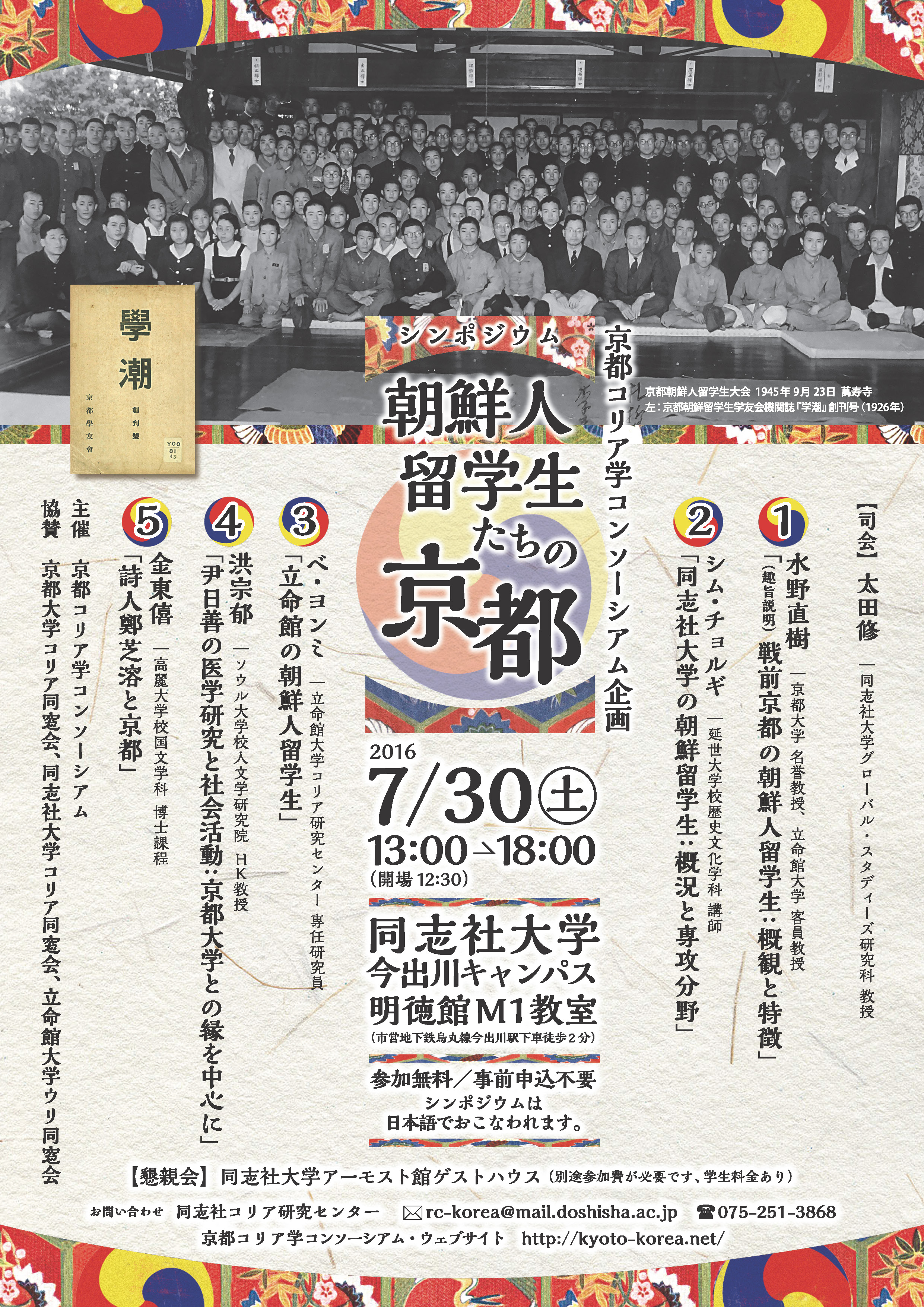
※チラシのダウンロードはこちら
日時: 2016年7月30日(土) 13:00~18:00 (開場12:30) ※参加無料、事前申込不要
場所: 同志社大学今出川キャンパス 明徳館M1教室(会場への行き方はこちら)
※京都市営地下鉄烏丸線・今出川駅下車・1・3番出口から徒歩2分(交通アクセスはこちら)
司会:
太田修(同志社大学グローバル・スタディーズ研究科 教授)
発表:
1. 水野直樹(京都大学 名誉教授、立命館大学 客員教授)
「(趣旨説明)戦前京都の朝鮮人留学生:概観と特徴」
2. シム・チョルギ(延世大学校歴史文化学科 講師)
「同志社大学の朝鮮留学生:概況と専攻分野」
3. ベ・ヨンミ(立命館大学コリア研究センター 専任研究員)
「立命館の朝鮮人留学生」
4. 洪宗郁(ソウル大学校人文学研究院・HK教授)
「尹日善の医学研究と社会活動:京都大学との縁を中心に」
5. 金東僖(高麗大学校国文学科・博士課程)
「詩人鄭芝溶と京都」
※発表は主に日本語で行なわれます。
懇親会: 同志社大学アーモスト館ゲストハウス
※別途参加費が必要。学生料金あり。
主催: 京都コリア学コンソーシアム
協賛: 京都大学コリア同窓会、同志社大学コリア同窓会、立命館大学ウリ同窓会
【お問い合わせ】
・同志社コリア研究センター E-mail: ![]() Tel: 075-251-3868
Tel: 075-251-3868
・京都コリア学コンソーシアム(KCKS) HP: https://kyoto-korea.net/
シリーズ「グローバル・ジャスティス」第47回
——————————————————————————————-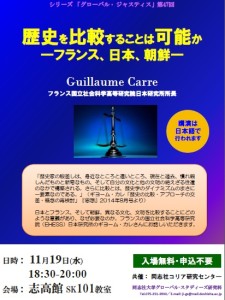
◆講演者 ギヨーム・カレ
(Guillaume Carre、フランス国立社会科学高等研究院日本研究所所長)
◆日時:2014年11月19日(水)18:30~20:00
◆場所:志高館SK101教室
◆テーマ「歴史を比較することは可能か-フランス、日本、朝鮮」
「歴史家の眼差しは、身近なところと遠いところ、現在と過去、慣れ親しんだものと新奇なもの、そして自分の文化と他の文明の絶えざる往還のなかで構築される。さらに比較とは、歴史学のダイナミズムのまさに一要素なのである。」
(ギヨーム・カレ「歴史の比較・アプローチの交差・概念の再検討」『思想』2014年8月号より)
フランスと日本、そして朝鮮。異なる文化、文明を比較することにどのような意義があり、なぜ必要なのか、フランスの国立社会科学高等研究院(EHESS)日本研究所のギヨーム・カレさんにお話しいただきます。
(※日本語で講演、質疑)
◆入場無料・申込不要
◆共催:同志社大学グローバル・スタディーズ研究科、同志社コリア研究センター
http://global-studies.doshisha.ac.jp/news/2014/1106/news-detail-139.html
——————————————————————————————
国際学術大会 「東アジアの他者認識と東アジア言説の課題」
—————————————————————————————
日時: 2014年9月19日(金)15:00~18:00、20日(土)10:00~18:00
場所: 同志社大学弘風館地下会議室
主催: 国際比較韓国学会・仁荷大学校韓国学研究所・同志社コリア研究センター
入場無料・申込不要
—————————————————————————————–
●第1部 京都留学生の文学世界に表れた東アジアの他者認識(9月19日、15:00~18:00)
基調講演「京都留学時代の鄭芝溶と詩作-植民地下の分裂を抉り出す―」(太田修、同志社大学)
報告①「『学潮』にみる京都の留学生社会と文学―『学潮』第2号の紹介を中心に―」(鄭鍾賢、仁荷大学)
報告②「大文字の尹東柱と抵抗性の深度」(張哲煥、延世大学)
報告③「金煥泰批評の有機体的問題設定」(呉瀅燁、高麗大学)
●第2部 東アジアの他者表象と文化翻訳(9月20日、10:00~16:00)
基調講演①「‘私’が達成すべき‘彼’の完成―東アジア人の他者認識と冒険のある地点について―」(鄭明敎、延世大)
報告①「ラインの彼方、他者の発見―玉川一郎の『京城・鎮海・釜山』(1951)にみる空間性と他者認識を中心に―」(朴俊炯、仁荷大学)
報告②「東アジアの文化芸術に対するフランスの重層的観点―ケ・ブランリ美術館(Musée du Quai Branly)の事例を中心に―」(鄭義鎭、祥明大学)
(昼食)
基調講演②「死を記憶する―金素月の場合―」(金萬秀、仁荷大学)
報告③「植民地期の日朝合作映画について―今井正/崔寅奎の『望楼の決死隊』(1943)・『愛と誓ひ』(1945)を中心に―」(渡辺直紀、武蔵大学)
報告④「『女子読本』と張志淵の翻訳」(徐黎明、南京大学)
報告⑤「二つの『血の涙』―日韓同名小説を通じて見る対外認識―」(和田とも美、富山大学)
●第3部 東アジアの近代についての思惟―後進性・植民地性・普遍性―(16:30~18:00)
報告①「進化、後進性、第1次世界大戦」(金東植、仁荷大学)
報告②「倒錯的普遍と近代の決算」(趙強石、仁荷大学)
報告③「周辺の近代―南北朝鮮の植民地半封建論を再考する―」(洪宗郁、同志社大学)
※報告はコリア語/レジュメは日韓両言語/通訳は討論のみ
特別研究会
「二つの訪朝団が見た平壌―中ロとの関係を強める経済動向を中心に―」
李明博政権発足以来、南北朝鮮の関係は閉塞し、昨年には戦争事態を激発しうる武力衝突(延坪島事件)にまで至り、日米韓協調による朝鮮民主主義人民共和国 (共和国)包囲が強められました。それに対する対応として、共和国は中ロとの関係強化へと大きく舵を切り、最近、金正日委員長の連続した中ロ訪問が行われ ました。
2012年は国際政治ならびに南北朝鮮政治の大きな転換点になるものと言われていますが、おりしも、最近訪朝した報告者2名による最新 朝鮮事情および現状分析を聞き、中国、ロシアの視点からの検討も加えて、経済的変化を中心とした深層的な分析と議論を行い、日本政府の選択と進路、日本の 市民の朝鮮半島、共和国認識に関して議論を深めるべく、 以下のごとく、特別研究会を企画いたしました。 (続きを読む・・)
category: シンポジウム